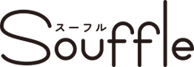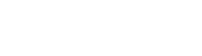『親なき後』のわが子のために~「ムーちゃんと手をつないで」みなと鈴×鹿内幸四朗対談
親がなくなった後、遺された子どもに障害がある場合どうすればいいのでしょうか? 子どもの生活、お金、相続など、心配なことはたくさんあります。スーフルでは『ムーちゃんと手をつないで~自閉症の娘(キミ)が教えてくれたこと~』著者のみなと鈴先生と、書籍『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』著者の鹿内幸四朗先生の対談が実現!! みなと先生と相続のプロである鹿内先生は、ともに障害のある子の親であるという共通点を持ちます。司法書士法人ソレイユの代表である杉谷範子先生にも同席いただき、おふたりに「親なき後」について語っていただきました。

監修:鹿内幸四朗・杉谷範子・
武石朋子(一般社団法人日本相続知財センター本部 行政書士)・
友田純平(司法書士法人ソレイユ、一般社団法人実家信託協会 司法書士)
取材・文:赤沼美里 カメラマン:竹中智也
親なき後の問題と成年後見制度
──みなとさんは、お子さんの「親なき後」について考えるようになったきっかけは何だったのでしょうか?
みなと:娘は重度の知的障害があるので、いずれ自分たち親がいなくなった後のことを考えざるを得なかったんです。でも、法定後見制度を利用したくないと思ったんですよね。法定後見人に他人がつくと子どもの財産管理に親が関われなくなるからです。
たとえば法定後見人に子どもの通帳の開示を拒否された場合、親であっても入出金明細を確認することも出来なくなりますし、子どものためにと貯めてきた預金からいくらか引き出して、子どもの好きなものを買ってあげたいと思っても「必要ない」と後見人に預金の引き出しを拒否されることだって考えられます。親なき後は毎月お小遣いとして少しずつ引き出して、好きなお菓子を買ったり、遊びに行ったりする時に使ってほしいなど、子どもの小さな幸せを願って貯金をしていたとしても法定後見人に「無駄使いだ」として引き出しの拒否をされてしまったら子どものその小さな幸せのためのお金も使えなくなるリスクがあるんですよ。おかしいですよね。でも本人の財産を減らさないということが仕事である法定後見人に、そういった嗜好品や余暇活動費など生命維持に直接必要ないと思われる支出は拒否される可能性だってあるわけです。
 こうした現実を踏まえると、成人年齢が18歳に引き下げられたこともあり、これに合わせて準備しなければと思いました。親権がある間にできることを考えたんです。
こうした現実を踏まえると、成人年齢が18歳に引き下げられたこともあり、これに合わせて準備しなければと思いました。親権がある間にできることを考えたんです。
鹿内:成年後見制度とは、判断能力が不十分な人について後見人と呼ばれる人がつき、財産管理や契約の支援をする制度ですが、大きく「法定後見」と「任意後見」とに分かれます。
法定後見は、家庭裁判所が後見人を決めるんですよ。つまり、我々親は決められないということ。家庭裁判所の公表しているデータから「本人」と「後見人」との関係を見ると「後見人」に「親族以外」が選任された割合が80%となっています。もちろんいい人が後見人となれば問題ありませんが、そうでない可能性もあるわけです。一方、任意後見は、子どもの親権があるうちであれば親が任意後見人を公正証書による契約で決めることができます。

──法定後見人がついたら、親は具体的にどんなことができなくなるのですか?
鹿内:法定後見人が選任されると、子どもの財産管理に関する決定権は親から後見人に移ってしまいます。後見人は「子どもの財産は子どものためだけに使う」という原則に従って行動するため、たとえば親の介護費用にも使えません。
もちろん、いい後見人に当たれば、子どもの幸せのために財産を使ってくれるはずだと思いますよ。ただし、確実に「いい人」がわが子の後見人になってくれるとは限らないのが現実なんです。これから先、ルールや法律がどう変わるかも誰にもわかりません。今後、制度がよりよくなることを願っていますが、今の政治や社会の状況を考えると、私たちのような社会的弱者にとって望ましい改正がなされるだろうと楽観視できない部分もあります。
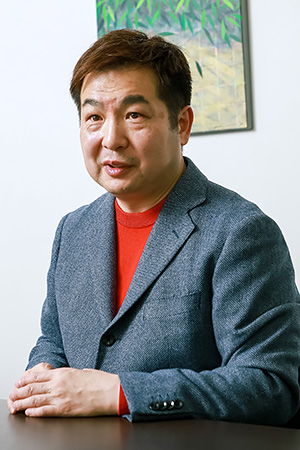 だからこそ、現行ルールの中でできる最善のリスクヘッジを考えました。親権を使った任意後見契約は、今の制度で認められているうえ、親が親権を持つ未成年の間にしか公正証書として契約できません。それに気づき、私は行動に移したわけです。ただし、すべての知的障害のある子の親が、未成年のうちに任意後見をすればいい、というわけではないとも思っています。
だからこそ、現行ルールの中でできる最善のリスクヘッジを考えました。親権を使った任意後見契約は、今の制度で認められているうえ、親が親権を持つ未成年の間にしか公正証書として契約できません。それに気づき、私は行動に移したわけです。ただし、すべての知的障害のある子の親が、未成年のうちに任意後見をすればいい、というわけではないとも思っています。
子どもを取り巻く財産状況、不動産の有無や生命保険のかけ方、祖父母の資産状況など、考えるべき点はたくさんあるからです。なかでも予測がつかないのは、人が亡くなる順番ですよね。親自身も年を重ねていきます。親の認知症対策が子どもの財産管理にも影響しますし、法定後見人の「なり手」が少なくなっていることも課題です。
家庭裁判所も、財産がそれほど多くない場合など一定の条件を満たせば、親が法定後見人になることを認めるケースは少なくありません。ただ、財産管理と身上監護を分けて、家族と専門家でそれぞれ後見人を立てることもあり、一概に親が『なれる』とは言い切れない。この「ケースバイケース」こそが、やっかいな点だと思います。
つまり、それぞれの家庭の財産状況や環境によって最適な答えは異なるということ。だから私は、将来が見通せないからこそ、少しでも安全策を取るべきだと考えました。それが、親権を使った任意後見契約(親心後見)を決断した最大の理由です。
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分な人を保護・支援するための制度です。認知症の高齢者が圧倒的に多いのですが、若い知的障害者も「判断能力がない人」という同じカテゴリーで扱われてしまう。成年後見制度自体に、さまざまな問題点があるんですよね。

成年後見制度の問題点
鹿内:法定後見では、持っている金銭や株などが多ければ多いほど、後見人への報酬額が増える仕組みになっています。親は何のためにお金を貯めていたのかと思うでしょう。
杉谷:法定後見がつくと、5年間で約半分の不動産が売られて金銭に変えられたというデータもあります。親が「この家で子どもにずっと暮らしてほしい」と願っていても、それが難しい場合もあるかもしれません。
──ひどい……後見人を見張るシステムはないのですか?
鹿内:自宅を売る行為は家庭裁判所の許可が必要ですが、自宅以外の不動産は後見人の判断で売却可能です。また後見人は「片道切符」で、本人が亡くなるまで続くんですよ。リスクを知っておくことが重要ということですよね。
※後見人が亡くなっても、本人が生きていれば後見は続いて、家庭裁判所が新しい後見人を選びます。
杉谷:高齢者の場合は、亡くなると相続人が通帳などをチェックでき、不正が発覚することもあります。障害者の場合、存命中は家庭裁判所がチェックしますが、チェックもれがある可能性も否定できません。それに、そもそも不正をしなくても毎月決まった報酬がかかってしまう仕組みになっていますからね。
──それは本当に制度の問題ですね。親なき後も子どもが幸せに暮らすためにと、一生懸命働いて節約して貯めたお金が、こうした形で減っていくのはつらすぎます。
具体的な対策
みなと:だから私の場合は、法定後見人をつけなくても、いざとなれば親が後見人となってさまざまなことを子どもに代わり意思決定できるように、鹿内さんが実践された「親心後見」を選択しました。
家庭裁判所に選任してもらった特別代理人とともに、私たち夫婦がそれぞれ子どもの法定代理人として公証役場に訪問し、親子間で任意後見を結びました。
詳しくはエッセイ漫画「わたしの終活!~元気なうちに任意後見・遺言書~」に描いていますが、私と特別代理人が【子どもの代理人】となって夫と子ども間で任意後見契約を結び、同様に夫と特別代理人が【子どもの代理人】となり私と子ども間で任意後見契約を結びました。鹿内さんが実践された「たすき掛け」のような任意後見契約です。

鹿内:法定後見で家庭裁判所が、障害特性を理解し、障害のある子に寄り添ってくれる後見人を選んでくれるとは限らないので、親心後見で親が優先的に後見人になれるようにしておくのです。そして、親心後見だけでは十分ではないので、私は親心後見に、遺言と生命保険をセットで考えてほしいと、お伝えするようにしています。
遺言がなければ、相続人全員で遺産分けの協議をする必要があり、そのため障害のある子に後見人をつける必要性が高まります。遺言があれば、協議は不要ですが、遺留分という遺言があっても支払わなければならない、法律で決められた最低限の取り分の問題になります。最低限の対策として遺言は作成したほうがよいでしょう。
みなと:我が家も夫と私で遺言書をつくり、お互いの全財産を配偶者に残すようにしました。ただし遺留分は、子どもに法定後見人がついた場合は請求される可能性があるので、遺言書に付言事項をつけました。
赤沼:遺言書は自分で書いたものでも有効なのですか?
鹿内:自筆証書遺言であれば自分で書くことができます。ただし、形式に不備があると無効になることもあるので、より安心な公正証書遺言を検討したほうがよいでしょう。ちなみに、遺言は何度でも作り直すことができ、最新のものが有効になるので、家族環境や資産状況が変わったら見直すといいですね。状況が変われば「作り直せる」「取り返しがつく」ところが遺言の強みだと考えています。
みなと:私たち夫婦の場合は、鹿内さんが本部専務理事を務めていらっしゃる日本相続知財センターさんの最寄りの支部に相談しながら準備しました。費用はかかりましたが、司法書士さんにお願いしたので安心感が違います。ただ、まず自分で勉強して理解してから専門家に相談したほうが納得のいく対策ができると思います。

お金をかけずにできる対策
鹿内:お金のかからない対策もあって、以下のようなものがあります。
●成人前に親権を持つ親が子ども名義の通帳を複数作る
●マイナンバーカードを作る
●15歳以上になったら、実印を作って印鑑登録することにチャレンジする
●生命保険の受取人が障害のある子になっている場合は「受取人」の再検討をする
●親や祖父母の資金により作成した子ども名義の預金がある場合、取り扱いについて再検討する
鹿内:銀行のキャッシュカードも磁気不良になることがあります。それを変更するには本人を連れていかなければならず、その瞬間に後見人が必要という話になりかねません。
みなと:驚いたことに、銀行口座を開設するのにも銀行ごとに年齢制限があるんです。親権があっても子どもの年齢が、銀行が規定している年齢を超えると銀行によっては親だけでは子ども名義の口座を開設できないこともあります。わが家は子供名義の口座を一つしか持っていなかったので他行にも開設しようとした時、「14歳以上の場合はお子さん本人によるお手続きが必要ですのでご本人を連れてきていただかないと…」や「基本的にはご本人に判断能力がないと口座開設はできません」とはっきり言われたこともあります。そのため我が家は親のみで親権を使って口座開設ができる銀行にしました。
 鹿内:ゆうちょ銀行は18歳まで親権で口座開設できるので、郵便局、両親のメインバンク、そして磁気不良の心配のないネットバンクを含め、複数の口座を作っておくことをお勧めします(決して大金を入れておいてください、ということではありません)。
鹿内:ゆうちょ銀行は18歳まで親権で口座開設できるので、郵便局、両親のメインバンク、そして磁気不良の心配のないネットバンクを含め、複数の口座を作っておくことをお勧めします(決して大金を入れておいてください、ということではありません)。
──子育てで忙しい中、こういった準備は難しいのではないですか?
鹿内:確かに忙しいと思います。親権があるうちにしかできない対策もあります。優先順位を決めて取り組むといいと思います。我が家の場合は、中3の春休み(卒業式が終わってから)から、高校1年のあたりに対策実行しました。理由は、その時期がママのPTA活動が激しくない時期だったからです(笑)。
優先順位がよくわからない。わが家の場合はどうしたらいいの?とよく相談を受けます。今はwebで相談も可能です。障害者特性をよく理解した専門家を見つけておき、相談できるところを確保しておくと安心かと思います。もちろん、セカンドオピニオンも大切です。
みなと:私も最初から全部をやったわけではありません。インターネットで情報を集めたり、本を読んだりして少しずつ理解を深め、できることから始めました。特に重要なのは、ご夫婦で話し合うことだと思います。両親が同じ考えを持っていれば、子どもの将来もより安心できますから。それに自分がいつ認知症になるかもわからない。元気なうちに進めていくのがいいかなと思っています。シングルのご家庭でも信頼できる親族の方などと情報を共有しておくのがいいのではないかと思います。ノートにいろいろ書き残しておくのもいいですよね。

親心後見にはデメリットも
──親心後見をすることにデメリットはないのでしょうか。
みなと:もちろんデメリットもありますよ。まず裁判所とのやり取りは素人にはハードルが高いので司法書士さんなどのサポートしてくれる専門家に依頼する必要があり、公証役場での支払いもあるので費用がかなりかかります。また、たとえばお子さんが、騙されて契約してしまっても任意後見契約をしているだけでは無効化できません。印鑑登録や相続放棄を子ども本人ができるなら、お金をかけて親心後見をしておいてもメリットはないかもしれません。お子さんの特性によるんですよね。
鹿内:どの制度を使うかは、家族構成や資産状況、そしてお子さんの特性によって変わります。きょうだいがいれば財産を託す選択肢もありますが、きょうだいの配偶者含めて信頼できるか注意が必要です。知的障害も一人ひとり特性が違うので、それに合わせた対策が大切ですよね。
みなと:そうなんです。その子の得意なことや苦手なことはさまざまですよね。お金の計算はできなくても、日常生活の判断はある程度できる子もいますし、計算はできても社会性に課題がある子もいます。そうした特性に合わせた対策を考えることが大切だと思うんです。
──本当にケースバイケースなんですね。こういった情報が特別支援学校などでもっと共有されるといいのですが。
鹿内:そこが大きな問題なんです。特別支援学校では、お金の話はあまりされません。私がセミナーを始めたきっかけも、娘が通う特別支援学校でPTA副会長をしていた妻の友人たちが「鹿内家で何をしたの?」と反応したことでした。学校では、将来の財産管理や親なき後の制度については、あまり触れないから誰もわからないんですよ。
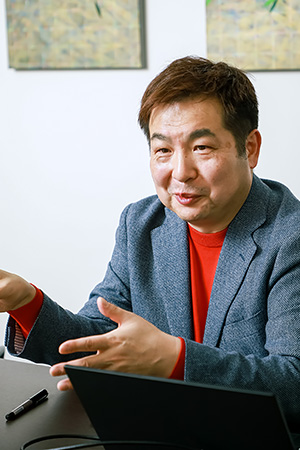 みなと:わかります。娘も特別支援学校に通っていますが、保護者向けの勉強会や懇親会では、思春期の対応など目の前の課題はたくさん話し合われるのに、親なき後の財産管理や後見制度についてはそこまで詳しくは触れられません。私が本当に知りたかった情報は、学校では得られなかったので自分で勉強するしかなかったんです。
みなと:わかります。娘も特別支援学校に通っていますが、保護者向けの勉強会や懇親会では、思春期の対応など目の前の課題はたくさん話し合われるのに、親なき後の財産管理や後見制度についてはそこまで詳しくは触れられません。私が本当に知りたかった情報は、学校では得られなかったので自分で勉強するしかなかったんです。
──それは残念ですね。特に知的障害のあるお子さんの親御さんは日々の生活でいっぱいいっぱいなのに、こんな複雑な制度のことまで自分で調べなければならないなんて。
鹿内:だからこそ、私は情報を広めることに力を入れています。学校や行政が動かないなら、親同士の情報共有が重要なんです。残念ながら専門家の中には「後見ビジネス」と捉えている人もいる。だからこそ、親の立場から声を上げ続けることが大切ですよね。
みなと:多くのお父さん、お母さんは「そんなこと考える余裕がない」状態です。でも、子どもの将来のために、少しでも時間を作って知識を得ることが本当に大切だと思うんですよ。私も知り合ったお母さんには「親権がある間に銀行印を作って子供名義の口座だけはいくつか作っておいたほうがいいよ」と伝えるようにしていますね。障害年金の受け取りなど本人名義の口座が必要になった時に使える口座を持っていないとその時点で後見人が必要になってしまうかもしれないので…少しずつでも情報が広がることを願っています。
──まずは、知らなければ始まらないですね。これだけ制度の正しい理解が低い中で、手間を惜しまずに行動されていて、そのエネルギーはどこから湧いてくるのでしょうか。
鹿内:私が親なき後対策にこれほど情熱を注いでいるのは、自分自身の経験から出発しているんです。私が話せるのは、自分で考えたことと体験したことだけですから。前例がないことに挑戦するからこそ、自分でしっかり調べ、複数の専門家にも相談して考え方を整理し、最終的には自分で決断して行動する。それが大切だと思っています。

知的障害のある子どもは、法律について自分で理解し、選択することはできません。だからこそ、親が優先順位をつけて決めるしかないんです。制度が「おかしい」と感じたとしても、世の中のルールをすぐに変えることはできません。私たちにできることは、ルールをきちんと理解し、その中で適切なタイミングで考えられる最善の選択をしていくことですよね。
最終的な責任は親にあります。どの専門家の意見を信じて、何を選び、何を選ばないのか。それも親が決めるべきことなんですよ。だからこそ、親は情報を集めてしっかり考える必要があります。
私たちが障害のある子の親御さんから聞いて、一番うれしかった言葉は「相談できるところを見つけました!」という一言です。親が孤立せず、相談できる場所があるということが何よりも心強いのだと思います。
みなと:本当にそうですよね。私自身も、重度の知的障害のある子の母として、子どもの財産を赤の他人に管理されることへの不安から行動を起こしました。子どものために残したお金が、後見人への支払いで減っていくことを想像すると、どうしても許せなかったんです。親としてできることはすべてやり切りたい、その一心で今も対策を続けています。
まずは知ること、そして時間をきちんと作ることが大切です。子どもが18歳になるまでに考えておくことが一番重要です。十数年間あれば本1冊ぐらいは読めるはずです。「このままでも大丈夫だろう」ではなく、どこかで真剣に考える時間を持ってほしい。時間だけは取り戻せませんから。自分の子どもにとって何が最適かを親自身が考え、準備することが大切だと思います。

プロフィール
みなと鈴
自閉症の第1子と定型発達の第2子の2児を育てながら月刊エレガンスイブにて「ムーちゃんと手をつないで~自閉症の娘が教えてくれたこと~」を執筆中。
鹿内幸四朗
一般社団法人日本相続知財センター本部専務理事
『障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本』著者
杉谷範子
司法書士法人ソレイユ代表、一般社団法人実家信託協会代表
「ムーちゃんと手をつないで~自閉症の娘が教えてくれたこと~」試し読みはこちら
自閉症や発達障害がよくわかるコラム「ムーちゃん通信」はこちら
今後の最新コンテンツが気になる方は、ぜひSouffle公式Xをフォロー!
ご感想フォーム
人気記事
 0
0
 0
0
 0
0
 0
0
 0
0

 @Souffle_life
@Souffle_life